『リトルバスターズ! エクスタシー』二次創作と愛の痕跡(神北小毬ルート)

「あなたの目が、もう少し、ほんのちょっとだけ見えるようになりますように」
視界に映るもの。個々人によって、その見え方はきっと異なるのだろう。それは、肉体の状態(視力など)に起因するものから、そうでないものも挙げられる。例えば、ある人にとっては、ただの桜でも、別の人にとっては、学生時代の思い出が詰まったものかもしれない。
だから、「目がよく見える」というよりは「目の見え方が違う」と言ったほうがいいだろう。
神北小毬は言う。子どもの頃、『フランダースの犬』を見たと。原作では、ネロはパトラッシュと一緒に天に召されていくが、彼女が見たものはそうではなかった。ネロもパトラッシュも死ぬことはなかった。誰もが死なない。そんなハッピーエンド。
物語としては破綻しているかもしれない。それでも、彼女はそんな物語が好きだという。何故なら、ハッピーエンドで終わったということは、誰かが幸福であったほしいと望んだから。きっと、その背景には誰かの愛があるから。
私たちの目の見え方は違う。だから、世界を切り取るにしても、その切り取り方は異なってくる。小毬は日常のなかに素敵なものを見出し、日々の風景を鮮やかなものに変えていく。
そう、彼女は詩人だ。詩を作るからではない。ありふれた意味のなかに、異なる文脈を見出すから。
では、彼女だけが詩人なのか? そうではない。
小毬が見た『フランダースの犬』。それはある種の二次創作だ。
作り手の想いは分からない。当人ではないから。見え方が違うから。それでも、小毬のことを信じるならば、そこには愛があった。彼らに幸せであってほしいという思いが。
ならば、愛は普遍的なものだ。『フランダースの犬』だけではない。さまざまな二次創作、その背後に愛の痕跡を見出せる。
この世界には見たくないものも溢れている。見えすぎるがゆえに見えてしまうもの。悪意や死。
たくさんの物語。それが愛の証左とは限らない。それでも、そこに善意があること。それを信じることぐらいは出来るかもしれない。
『リトルバスターズ! エクスタシー』名前の宿命を拒むこと、よき歯車とは(能美クドリャフカルート)

ライカ(ロシア語: Лайка、1954年 - 1957年11月3日)は、宇宙船 スプートニク2号に乗せられたメスの犬の名前。地球軌道を周回した最初の動物となった。
能美クドリャフカ。彼女の名前の由来は、地球軌道を周回した最初の動物、クドリャフカ(ライカ)にある。
彼女の母は宇宙飛行士だった。クドは祖父と共に各国を転々しており、母といる時間は少なかった。それでも、彼女は宇宙に惹かれ、やがて、自分もそうなりたいと願うようになった。しかし、彼女はライカにはなれなかった。
クドリャフカの名前を冠している。けれど、ライカにはなれない。日本人離れした容姿をしている。が、内面はそうではない。周囲からのまなざしと内面の齟齬。それは彼女を苦しめた。
クドルートの冒頭。理樹とクドたちはテストに備え、勉強会を開くことになる。クドは英語を苦手としており、日々、教室で理樹たちと勉強に励んでいた。が、クラスの一部の人はそれを面白がっていた。そう、日本人離れした容姿をしていながら、英語(外国語)を苦手としていること(ここで重要なのは日本人離れした容姿をしているからといって、外国語が得意でなくてはならないかと言われれば、そうではなくて、彼らのなかでそういった認識が形成されていることにある)。彼らの目にはそのギャップが滑稽に映ったのだろう。
クドは苦悩する。自身だけではなく、一緒に勉強している理樹を奇異のまなざしに巻き込んでしまうことに。けれど、理樹は手を伸ばし続ける。クドはクドだと。
そうして、時間を重ね、二人は恋仲になる。が、穏やかな時間はそう長くは続かなかった。
彼女の故郷、テヴァ共和国でロケットを打ち上げるという報道があった。そして、クドの母親もそれに搭乗すると。しかし、ロケットの打ち上げは失敗した。テヴァ共和国の情勢は混乱を極める。
今、向かえば、二度と戻ってくることは出来ないかもしれない。それでも、理樹は彼女の背中を押し、クドは祖国へ向かう。母親に会うために。
テヴァに着いたとき、彼女の眼に飛び込んできたものは過酷な現実だった。彼女は母親の姿を探す。少しでも、自分に出来ることをしながら。やがて、彼女は祖父と再会するも、反乱軍につかまってしまう。そして、反乱軍の一人は告げる。あのライカのように、祖国のための礎となってもらうと。
クドリャフカはよき歯車でありたいと願っていた。世界はいくつもの歯車から構成されていて、そのなかで粛々と自身の務めを果たす、そんな存在に。そう、あのライカのように。
本当にそうだろうか。恐らく、そうではない。彼女は自分の犬にこう名付けていた。ストレルカと。大きいのに、ストレルカ(小さい矢)。名前と実質との不一致。
西園美魚が語るように、名前とは一義的なものではない。クドリャフカという名前に「祖国のための礎となった、よき歯車」という意味を見いだすものもいるかもしれない。だが、それはあくまでも一面にすぎない。そう、クドがその名前に殉じる必要はないのだ。
ゆえに、奇跡は起こった。起こらなければならなかった。彼女がクドリャフカであるからこそ、「祖国のための礎となった、よき歯車」で終わってはいけない。よき歯車であること。それは名前の宿命に殉じることではない。他者からの意味付けを内面化するのではなく、自分がどうありたいか。それを再定義することにある。
能美クドリャフカ。ライカの名前を背負い、それでも、宇宙に行きたいと願う。誰かの意志ではなく、自分の意志で。もう、彼女を縛り付ける枷はないのだから。
引用
https://www.weblio.jp/content/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%AB%E7%8A%AC
『リトルバスターズ! エクスタシー』有限な生、始まりと終わりの海。

「チーム名は...リトルバスターズだ」
棗恭介はそう宣言した。この日、ひとつの野球チームが発足した。メンバーは井ノ原真人、棗鈴、棗恭介、直枝理樹の四人。在りし日、自分を暗がりから連れ出してくれた、あの時と同じではない。それでも、また、「リトルバスターズ」の皆と一緒に遊べる。理樹はそのことに歓喜する。そして、いつまでもこんな時間が続けばいい と。そう願った。
しかし、「いつまでもこんな時間が続けばいい」この願いの裏側にはこの世の不条理、有限性がびっしりと張り付いている。終わりがあるからこそ、終わってほしくないと願ってしまう。だからこそ、その願いは終わりがあることを意識していることの裏返しだ。
それでも、楽しい日々は続いていく。最初は四人だった。少しずつ、その輪は広がっていく。腕に怪我をした謙吾を加え、新生「リトルバスターズ」が結成される。これからも、こんな日々が続いていく。そう予感せずにはいられなかった。
だが、そんな日々は終わりを告げる。個別ルートに入ると、リトルバスターズという集団は背景に退く(例外もある。来ヶ谷唯湖ルートでは、彼女への想いを自覚した理樹を助けるべく、リトルバスターズの面々(主に、謙吾、真人、恭介)が奔走する など)
やはり、皆との楽しい時間はいつか終わってしまうのだろうか。
さて、鈴ルート(Refrainルート)では、ある事実が明かされる。それは世界の秘密だ。修学旅行にて、彼ら(リトルバスターズのメンバー含む)は事故にあい、生死の境を彷徨っている。そんななか、理樹、鈴は真人と謙吾に助けられ、一命をとりとめた。生き延びたのは鈴、理樹の二人だけだった。そして、恭介らが理樹、鈴にこの過酷な現実に立ち向かうための力をつけるべく、一つの世界を構築する。それこそが、これまでの日々を過ごしてきた世界だったのだ。
そう、この世界は初めから、終わるために作られたものだった。
何事にも終わりはある。直枝理樹はそのことを良く知っていた。それでも、「いつまでこんな時間が続けばいい」そう願わずにいられなかった。
幼いころ、彼は両親を亡くしている。そして、彼は悟った。「生きることが失うことだ」ということを。
以来、彼は夢を見続けている。現実という夢を。きっと、彼が夢をみないのは夢を見てしまったら、その時点で、現実/夢という区分が成立してしまうからだろう。一度、そうなってしまったら、この世の過酷さと直面しなければならないからだ。だから、彼のナルコプレシーはこの世の過酷への防衛行動である。と言えるかもしれない。
生きることは失うこと。きっと、これはどうしようもない。生まれてしまうことの呪いだ。何故なら、生は死に向かっているから。誰とも関わりを持たずとも、自分と言うものが失われることは避けられない。
では、安らかな夢のなかに安住するのか? 理樹はそうしなかった。過酷を受け入れ、この世に「生まれ直す」ことを決意する。
そう、例え、いつかは失われてしまうものだとしても、もう一度、彼らに、リトルバスターズに会いたい。そう願ったから。かくして、理樹、鈴は夢から覚め、過酷な現実に立ち向かう。
だが、ここにはある種の困難がある。理樹は「生まれ直した」のであって、「生まれてきた」のではない。だから、これから、どうしようもなくこの世に産み落とされるものたち(本質的に、生命の誕生には非対称性がつきまとうと思う。個人的に。良い悪いではなく)が過酷をどう受け入れるかという問題をカバーできていない。
そこで、笹瀬川佐々美ルートを見ていきたい。
彼女のルートでは、彼女の過去の飼い猫が作り出した夢の世界のなか、理樹と佐々美がその作り手を探し出すという話だ。
そのなかで、こんなエピソードがある。幼少期、佐々美がこの町を引っ越したとき、飼い猫がどうしても見つからず、置いてきてしまった。後日、屋敷のあとを訪れるが、猫の姿はなく、彼女には深い後悔が残ったというものだ。
猫は生きていた。ここで重要なことは、親に置いて行かれ、孤独を感じた という境遇は理樹と重なるところがある ということだ。勿論、全くの同一視は危険だ(猫にはいなかったが、理樹にはリトルバスターズがいた)それでも、理樹は猫に自身の過去を重ね、例え、置いて行かれたとしても、親に会いたい。生まれてきたことを呪わないと。そう思った。
先述したように、生命の誕生には非対称性がつきまとう。理樹も過酷なこの世に産み落とされ、そして、両親に先立たれた。それでも、彼は自身の生を呪わない。
恐らく、過酷とは普遍的なものだ。そして、それでいて、個別的なものだ。だからこそ、個別ルートで、それそれのヒロインが抱える問題に異なるアプローチが要請される。そう、この過酷な世界に生命が誕生することを一概に肯定することはできない。
だが、少なくとも、この『リトルバスターズ』という作品のなか、彼らは有限であることを受け入れた。Refrain ルートのラスト。恭介の提案により、彼らは海を目指す。そう、美魚ルートで描かれたように、始まりにして、終わりの場所を。
きっと、これからも彼らは続いていくのだろう。有限な生のなか。どこまでも。
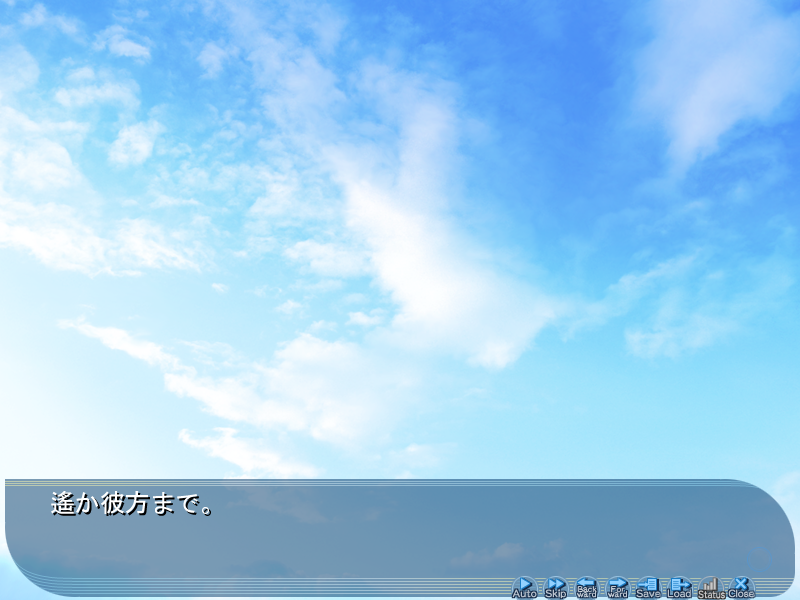
『Angel Beats!』どうしようもなく、過酷だった生を肯定すること

『Angel Beats!』では、死後の世界で、学園生活を送る人々の姿が描かれている。そして、彼らは未練を抱えている。
例えば、登場人物の一人、ゆりは裕福な家庭に生まれ育ち、幸せな日々を送っていた。が、ある日、その日々は崩れ落ちる。強盗が現れた。強盗は、ゆりに告げる。自分たちが気に入るものを持ってくることができなかったら、ゆりの下の子たちを一人ずつ殺していくと。そうして、彼女は妹たちを救うことができなかった。
かくして、ゆりは死後の世界を訪れた。妹たちを救うことができなかったという未練を抱えたまま。このように、それぞれが過酷な人生を送り、この世界を訪れている。そして、この世界で抗っている。過酷な生を齎した神に。この世界で生き続けることで。
では、彼らはこの世界で生き続けるのか。そうではない。彼らには未練がある。その未練が解消されれば、この世界を去るのである。
永遠の生。確かに、未練が解消されることがなければ、この世界で生き続けることは可能かもしれない。だが、彼らはそうしなかった。それぞれが、自らの意志で、自らの人生と向き合い、そのうえで、何らかのかたちで(彼らはそれぞれに異なる過酷を抱えていた。このような世界が成立している時点で、この世に過酷がありふれていることは分かる。しかし、一方で、過酷は固有性をはらんでいる。ゆりの過酷と音無の過酷はまた別のものだ。それゆえに、過酷を肯定できるのは本人でしかない。そして、そのかたちも異なる。恐らく、一致するのはそれを肯定したという事実だけで)、それを肯定している。
確かに、この世界には過酷がありふれている。そして、生命はこの過酷な世界に産み落とされてしまう。どうしようもなく。何故なら、生命を生み出すものと生み出されるもののあいだには非対称性がつきまとうからだ(良い意味でも悪い意味でも。少なくとも、自分はそう思う)
この物語は、今、過酷を抱えるものを救うとは限らない(何故なら、その過酷を肯定できるのは当人だけだから)けれど、この物語のなかで、少なくとも、彼らはその過酷な生を肯定することができた。どうしようもなく、そんな生を送ってしまったが(当人の意志、環境、さまざまなものが絡まりあって)それでも、肯定することができた。自らの意志で。
現世の生を肯定するのではなく、あくまで、個々人(『Angel Beats!』のキャラクター) の生の肯定に留まること。そこにこそ『Angel Beats!』の倫理があるのではないだろうか。
『Summer Pockets』 フィクションの夏、ノスタルジーの袋小路

夏休みと言えば、どんなものを思い浮かべるだろうか。友人と遊ぶ、虫取り、かき氷、駄菓子屋など。『Summer Pockets』においては、そのような夏の風景が描かれていた。しかし、自分は、現在に至るまで、そうした夏を過ごすことがなかった。ゆえに、この作品の夏の風景に「嘘らしさ」を感じた。
だが、それは嘘らしいものでありながら、どこかで見たことがあるような。そんな感覚を覚えた。そう、フィクションのなかの夏だ。具体的な作品が思い浮かんだわけではない。ただ、これまでに触れてきた作品のなか、そうして風景があったような。そして、自分もそれを体験してきたかのような、そんな錯覚を覚えてしまった。ある種のノスタルジーだ。
だからだろうか。自分は、この作品の舞台。鳥白島に居心地のよさを感じていた。気の置けない友人たちとの時間。そんな時間が続いてほしい。そう思った。
けれど、そうしてはいられなかった。
本作品の視点人物、鷹原羽依里。かれは、ある事情があって、島に逃げてきた。所謂、逃避行だ。そして、うみ。彼女も特別な事情を抱えて、この島に逃げてきた。
自分もそうかもしれない。フィクションに触れるとき、どこか遠くの世界に触れたい。そんな気持ちがある。だから、彼らに共感した。
彼らも、この夏が続いてほしい。そう願った。けれど、同時に、彼らは逃げてたくないとも思った。
この時間がずっと続いてほしい。きっと、永遠への渇望はこれに限った話ではない。
だが、永遠への渇望には矛盾がある。もし、永遠が実現された場合。時間という概念は意味をなすのだろうか。恐らく、時間というものが意味をなさなくなったなら、永遠への渇望という価値が損なれる。何故なら、その価値は時間というものに支えられているから。この時間がずっと続いてほしいという思いは、それが続かないからこそ、意味をなすものだ。
そう、鏡子さんが語るように、過去に戻れる力があるとすると、過去や未来の境目がなくなってしまい、どこにもいけなくなってしまうのである。
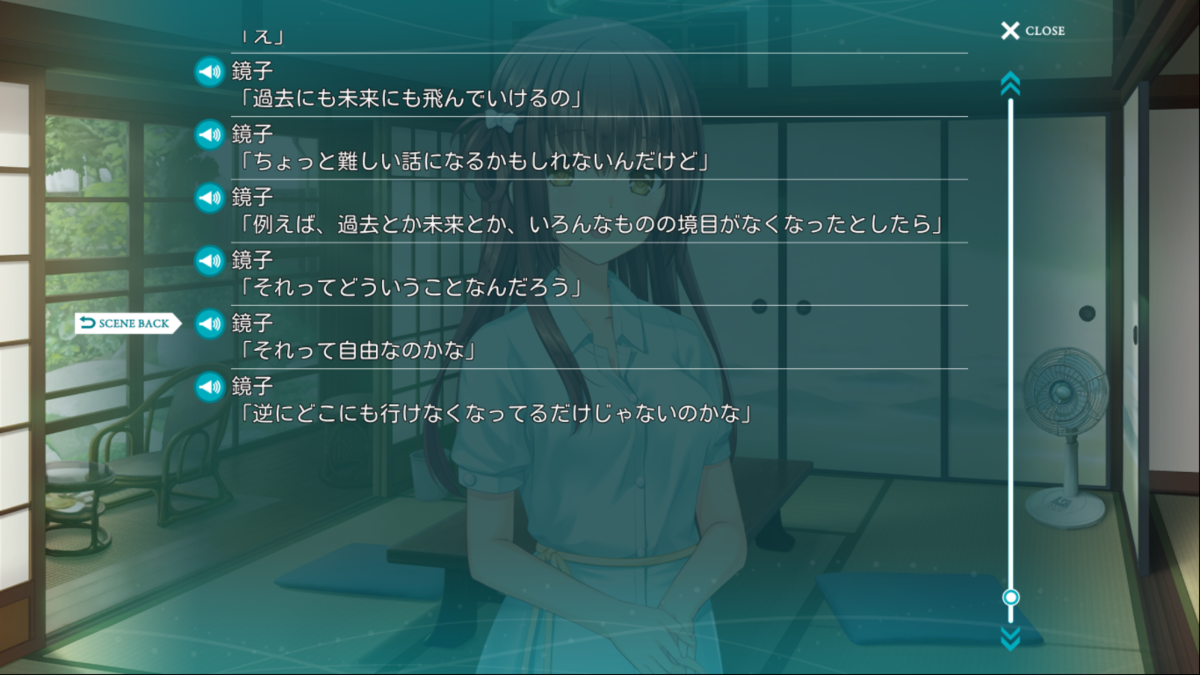
うみ、しろは は意識を過去に飛ばすための力を持っている。彼女たちは、酷薄な現在を受け入れるよりも、楽しかった時間に戻ることを選択してしまった。ノスタルジーのなかに浸ることを。そうして、この世界の時間の環は閉じてしまう。
が、永遠のなかにおいて、永遠への渇望は価値を損なう。どこかで、この環を終わらせなければならない。
『Summer Pockets』では、フィクションの夏へのノスタルジーが描かれると同時に、そこに内在する危うさ。つまり、ノスタルジーが袋小路に繋がりうることも描かれていた。
そう、いつかは現実に帰らなくてはならない。何故なら、夏休みは終わりがあるからこそ、夏休みたりえるように、物語も終わりがあるからこそ、物語たりえるのだから。
では、現実に帰らなくてはならないとき、物語での経験に意味はあるのか。
きっとあるはずだ。紬ルートで描かれていたように、終わりがあるとしても、そこには意味があるはずなのだから。
そして、夏が終わり、秋が訪れたとしても、来年の夏があるように。また、鳥白島を訪れることができるように。一つの物語を読み終えても、そこに帰ることができるはずだ。そう、羽根を休めるために。
『中二病でも恋がしたい!』七宮智音という在り方
前書き
考えを詰め切れていないところがありますが、書いておかないと忘れてしまいそうなので
中二病とは何か。この問いに対して、いくつかの答えが与えられるだろう。ここでは、『中二病でも恋がしたい!』の作中人物たちの姿から、その輪郭を捉えていきたい。
本作品には、元(微妙なところではある)中二病患者を含め、何人かの中二病患者が登場する。彼らに共通している点は何か。それは、自分は特別な存在である と思いこんでいることだ。ここで重要なことは彼らの信念が妄想であるかどうかではない。
中二病とは、ここではないどこか、ありえたかもしれない自分への憧れに根差しているのではないかということだ。
何故か。それは、先述したように、彼らが自分は特別な存在であると「思いこんでいる」からだ。このことは、実際には、彼らは特別な存在ではないことを示している。より正確に言えば、彼らの認識と他者の認識のあいだにはギャップがある。
そして、いささか、乱暴な言い方になるかもしれないが、憧れという感情はここにはないものに向けられるものなのではないだろうか(勿論、ここにあることに気付いていないという可能性もある)
ゆえに、このギャップこそが、遠くのもの(ここではないどこか、ありえたかもしれない自分)への憧れの証左と言えるのではないだろうか。
さて、本作品では、七宮智音というキャラクターが登場する。彼女も中二病患者の一人だ。かつて、中学時代、富樫勇太と智音は友人だった。勇太は彼女の姿に憧れ、中二病患者となり、行動をともにした。やがて、智音は勇太への恋心を自覚する。それと同時に、遠くのものへの憧れを失いつつあること。中二病から覚めつつあることに気付く。恋心か中二病か。智音は中二病を、魔法魔王少女で在り続けることを選んだ。
だが、高校生となり、六花と恋人関係になった勇太と再会する。そして、六花の姿を見て、智音はありえたかもしれない自分の可能性を垣間見、閉じ込めたはずの恋心を自覚する。
六花も中二病患者だ。にもかかわらず、勇太の傍にいる。それはありえたかもしれない自分で、そのことが智音を苦しめる。
さて、智音の苦悩は、中二病の根底にあるもの、ここではないどこか、ありえたかもしれない自分への憧れと通底している。可能性と現実のギャップ。これこそが、ここでの問題と言えるのではないだろうか。
では、可能性と現実のギャップ。この問題とどのように向き合えばいいのか。
七宮智音は決断する。かつて、富樫勇太と共に追い求めた、暗炎龍を自身の手で打ち倒すことを。
勿論、暗炎龍はいない。むしろ、彼女が戦うべき相手は恋敵の六花なのではないか。
そうではない。きっと、彼女の中で、心は既に定まっている。魔法魔王少女で在り続けるという思いは揺らいでいない。それでも、彼女が苦悩するのは、ありえたかもしれない自分を幻視してしまったからだ。
そう、幻視なのである。その憧れは彼女のなかにあるものであって、外にあるものではない。だからこそ、彼女が戦うべき相手は六花ではなく、己のなかにある、かつて、富樫勇太と共に追い求めた、暗炎龍という名の亡霊なのだ。
ありえたかもしれない自分。けれど、現実にはそうではない。そのギャップに悩まされることはある(少なくとも、自分は何度かあった)
七宮智音という在り方は、可能性と現実のギャップにどのように向き合えばいいか。その一端を示しているのではないだろうか。
後書き
中二病と七宮の接続が強引かもしれない。もう少し考えてみます。
最近の趣味、Vの話~『神聖にして侵すべからず』、フィクションによせて~
最近、「ヴァーチャル」とは何かということを考えさせられる。ひとえに、所謂「V
Tuber(以下、V)」に嵌まっていることが大きい。本当のところを言えば、かつての自分はVに偏見を抱いていた。元々、実況・配信文化が好きで、Vに嵌まるための下地のようなものは出来上がっていた。にもかかわらず、それに触れることを忌避していた。今となっては、その理由は分からない。きっと、逆張りだったのだろう。そう思えてしまうほど、Vに嵌まってしまった。
かくして、Vの配信(または、アーカイブ)を見ながら、絵の練習をすることが多くなった。それに伴って、エロゲ、読書をする機会が少なくなってしまった。勿論、興味が無くなったわけではない。今でも、フィクションは好き……なのだと思う。けれど、自分はどうしようもないほどに要領が悪く、どうやら、複数の趣味を横断することができないらしい。
そういう経緯で、「ヴァーチャル」とは何かを考えることが増えた。では、そもそも、「ヴァーチャル」とはどういう意味なのか。辞書の意味を引用するならば、「仮想の」という意味になるのだろう。けれど、どこか、しっくり来ない。何故か。それは、自分のなかで、Vの背景には実在の人間がいるという了解がされつつも、一方で、キャラクターとしての質感を伴っているからだ。そう、確かに、彼らはそこに存在する。少なくとも、自分にとっては。
ここで、奇妙な符号が生まれた。以前、『神聖にして侵すべからず』というゲームについての記事を書いたことがある。その作品のなか、こういう発言がある。
「会長にもらった鉄の花があるだろ?あれは確かに、本物の花じゃないけど、美しい花ではあるだろ?」
「それと同じように、王国は確かに、いわゆる実態はないけれど、何か人を引き付けるものがあるんだよ」
「見えない奴らには見えないままでいいのだ。だって、王国は確かにここにあるのだから」
少しだけ、確認したい。王国とは、ファルケンスレーベン王国という作中内の架空の王国を指す。作品外のものたちにとってのものだけではなく、作品内のものたちにとってもそうだ。王国は法的な措置のもと、認められたものではない。そこにあるのは、かつて、王国があったという事実だけだ。実態はない。あくまで、猫庭(作中の架空の土地)の人々、ひいては、そのほかの人々たちのなかで「ある」と了解されたものだ。
それでも、それらの人々たちにとって、王国は確かに「ある」 たとえ、ごっこ遊びのようなものだろうが、そこにあるのだ。
ここに符号が見出された。ごっこ遊びという言葉に反感を抱くものもいるかもしれない。それでも、自分にとって、Vは、実在の人間とキャラクター、それぞれの質感が浮かび上がってくるものなのだと。見る人(全員が全員ではないと思う。フィクションと同様、それにどういう態度で触れるかは各々の裁量によるところなので)のあいだで、「ある」と了解されたものなのだと。
『神聖にして侵すべからず』の瑠波ルートで語られる事柄は、どこか、フィクションの原理に通じるところがある。そう思っている。今の自分に、それを語りつくせるほどの知識も言葉もないが。
フィクションに触れるとき、私は、どこかで、それが無いものだということを了解している。無いと了解しつつも、あると「感じてしまう」そう、感じてしまうのだ。そう思えるほど、彼らには質感が伴っている。
私にとってのフィクションのキャラクターたち、ファルケンスレーベン王国の民にとっての王国、それらは区別できるものなのか。分からない。でも。近いものだと感じてしまう。
だからこそ、私にとって、瑠波ルートはフィクションの可能性を謳ったものだ。例え、一部の人々に後ろ指をさされるものであっても、誰かを救いうるのだと(同様に、呪いたりえるのだと)実在しないからこそ、為せることがあるのだと。
勿論、Vとフィクション。両者のあいだに、符号を見いだしてはいるが、全てが一致するわけではないだろう。Vの背景には実在の人間がいる。野暮ではあるが、そのことは事実なのだろう。
そのことがどういう違いを生むか。そこまでは分からない。けれど、そのことが実在の人間とキャラクターの奇妙な質感に繋がっている。そういう感覚がある。
今の自分とかつての自分、向いている方向は違えど(恐らく)、地続きなところもあるのだろう。